野外や草むら、山の中にはマダニがうじゃうじゃ潜んでいます。もし野外でキャンプ中、マダニに噛まれてしまっても、人里離れていれば病院も近くにありません。
「下山したら病院に行こう」とは思いつつも、そのままずっと身体にマダニが噛みついた状態で行動するのは気持ち悪いですよね。
かといって無理やり手で引きちぎると、マダニの口が皮膚に残ってしまいます。運が悪いとマダニの唾液が皮膚から人体へ逆流して、感染病にかかってしまいます。
マダニは噛みついてから2〜3日経過すると皮膚にがっちり口が挟まり取りにくくなりますが、噛みついた当日以内ならまだ取れやすいです。
その場合は、線香に火をつけて近づける取り方、塩を使った取り方を試してみましょう!
そのほかにも、犬などの動物に噛みついたときの取り方もご紹介します。
マダニの取り方なら蚊取り線香が便利!

マダニはとても小さく、一度皮膚に口を差し込むと取れにくい、厄介な生き物です。
そしてマダニの唾液には麻酔に似た物質が含まれており、噛まれてもすぐには気づきにくいです。
もし手や専用以外のピンセットなどで無理やり引っ張ると、マダニの身体と口がちぎれてしまい、口だけが皮膚に残ってしまいます。ちょっとしたホラーですね。
しかし線香を使えば、マダニの口が皮膚から外れやすくなります。キャンプや野外へ行くなら、蚊取り線香が使えますよ!
マダニの身体やお尻部分に火の付いた線香を近づけるか、押し当ててみましょう。皮膚に噛みついていたマダニがポロッと取れやすくなります。
私がマダニ対策をしていなかった頃に友達と登山に行った時の話です。マダニに噛まれてしまったのですが、線香を使った取り方が良いと聞いていたのですが私は持っていませんでした。
幸い、友達が蚊取り線香を持っていたので、蚊取り線香をマダニに近づけてマダニを外す事が出来ました。
わざわざ仏壇用の線香を買わなくても、キャンプの必需品ともいわれる蚊取り線香があれば安心ですね!
ライターやマッチなどで直接火を近づけてはいけない
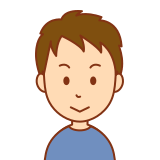
線香に火をつけるなら、ライターやマッチがいるよね。
あ・・・わざわざ線香でなくてもこれをマダニに近づけたらいいんじゃない?
ライターやマッチだと火が直接皮膚に当たり、逆にヤケドをしてしまいます。
マダニは火や熱に弱いのですが、直接火を近づけるのではなく、線香に小さな火を移して近づけます。
万が一線香の火が皮膚に当たってヤケドをしたとしても、ライターほど直接当たるわけではないので最小限のヤケドで済みます。
私も、キャンプや登山に行く際は線香を持って出かけるようにしています。もちろん、火をつけるライターやマッチも忘れずに♪
マダニは家にいるダニとは種類が違う!
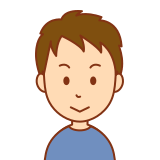
家でダニに噛まれたことあるけど、ずっと噛みついていなかったよ?
このマダニもいつか取れるんじゃないの?
マダニは、家庭内に生息するダニと種類が異なります。
家庭内で生息するダニは4種類います。この中でも人を刺すのは「ツメダニ」だけで、刺して吸血したら離れます。
しかし、マダニは家庭内に生息するダニとは異なります。
マダニは皮膚を切り裂いて噛みつきます。ギザギザした口がついているので、一度噛みついたら抜けにくいです。
直接引き抜こうとしても人間のヒフからギザギザの口が抜けないだけでなく、体が分裂してヒフに残ってしまいます。
また、直接叩くとマダニの唾液が人間の体内に逆流してしまい、感染症を持ったマダニの唾液が体内に入ってしまい病気になる恐れもあります。
そして、噛みついたらずーっとそのまま吸血し続け、体型も大きくなっていきます。
最初は目に見える大きさで約3~8mmくらいですが、血を吸い満腹になると約1〜2cmもの大きさになります。およそ倍に膨れるんですね(怖)
マダニの取り方なら塩も有効に使える!

実は、マダニが皮膚に噛みついてしまったときの「100%確実な取り方」はないんです。先程の線香を使った取り方も、「取れやすくなります」としか言えないんです。
もし線香で取れなかったら、「塩」も使えますよ!簡単な取り方を紹介します。
- 噛みついているマダニの上に、塩をたっぷり乗せる
- 水を少量かける
- 5分後、塩を取り除く
- ピンセットを使って、ゆっくりとマダニを皮膚からはがす
もし線香で撮れなかった場合のために、キャンプの調味料用に塩を持ってきておけば、ダブルで安心ですね♪
マダニの取り方ならワセリンも使える!

もしマダニが噛みついて1日以上経過してしまったら、マダニの口が皮膚にガッチリ挟まります。すると、線香や塩では取れにくくなります。
そんなときは慌てて手で引っ張ったりせず、マダニを窒息させて口を離させましょう。そのためには、ワセリン、軟膏を使った取り方がおすすめです。
ワセリンや軟膏をマダニにたっぷり塗り付けます。30分以上経過すると、呼吸が出来なくなったマダニは苦しくなり、皮膚から外れやすくなります。
ワセリンはもともと石油由来の油分でできており、肌に薄く塗ることで皮膚からの水分蒸発を防ぎます。
「水分の蒸発を防ぐ」ということは「空気の通り道も防ぐ」ということでもあります。
マダニも生き物なので、呼吸ができないと死んでしまいます。
ワセリンをたっぷり塗ってマダニの呼吸を妨げることで、「うっ、息ができない。・・・ぷはっ!」と皮膚から口を離してくれるのです。
マダニが犬に噛みついたときの取り方なら酢水を使う!

自分にマダニが噛みついてしまった場合なら自分でなんとかできますが、愛犬や愛猫、動物にマダニが噛みついてしまったら、少し慎重になりますね。
もし線香を近づければ毛に火が燃え移りますし、塩をたっぷり乗せると皮膚に染み込んで痛がるかもしれません。
自分以外の動物に噛みついた場合、一番痛みや被害が少ないのは酢を使った取り方です。それでも取れなければ、ピンセットや、先ほど紹介したワセリンを使いましょう。
- 水と酢を同量混ぜ合わせ、コットンに含ませる
- コットンをマダニに覆い被せ、10分おく
- コットンを離し、マダニをゆっくり外す
たったこれだけで、マダニがするっと身体から外れるんです!
酢を使っても取れない場合は、ピンセットで慎重に取ります。ひねりつぶさないように注意して、出来るだけヒフの表面に近いところをピンセットでつかみます。
マダニを取り除いたら、愛犬(愛猫)の皮膚と自分の手をよく洗い消毒をします。
マダニを取った後は2週間様子を見てあげよう
マダニは血を吸うだけでなく、伝染病や寄生虫を運ぶ厄介な生き物です。犬に感染した病気や虫が、人間や別の動物へ移り、重症化する危険性も持っています。
マダニを取ったあとは、感染や病気にかかっていないか、長くても2週間は注意深く観察してあげて下さい。
特に、犬の場合、気をつけるべき病気は「バベシア症」です。体内の赤血球にこの原虫が寄生すると、溶血性貧血(ようけつせいひんけつ)が起こり、命にも関わります。
また、マダニの吸血によって他の犬にも感染してしまう為、多動飼いしていたら症状が出ないと確認できるまで隔離した方がいいです。
私の家には、ゴールデンレトリバーの血をひく雑種の犬がいます。散歩が大好きでなのですが、散歩コースに草むらを通るコースがあります。
いつものように散歩をしていると、いつのまにかマダニが毛の中の皮膚に潜んでいたのです。。
大きく膨れ上がったマダニは家の愛犬の血をたくさん吸い、パンパンに膨れ上がっていました。
幸い、愛犬は病気になることはありませんでしたが、もし、病原菌を持っていたら…と考えたらとても怖かったです。
早くマダニを見つければ早期対処ができる!
マダニは、噛まれてから時間が経てば経つほど取りにくくなります。自分ならまだしも、犬や猫などの動物がずっと被害にあっているのは見ていられませんよね。
私たち人間もそうですが、マダニは早く見つけて早く取れれば、大事に至らず解決できます。
私がその後愛犬に対して、散歩の前後にやっている対策を紹介します。草むらが多いキャンプ地に連れて行くときにも有効です。
- 散歩の前には、マダニ用の薬を首筋にたらす
- 野原、草むら、畑、河川敷など、マダニがいそうな場所には近寄らない
- 散歩の後は、マダニが付いていないか体中をチェックする
- ブラッシングをする
- ダニ取りシャンプーを使用してお風呂にいれる
マダニは草地に隠れて、近くを通る動物の体温や呼吸、振動などで獲物を認識して飛び移ります。寄生リスクを避けるには、草むらには近寄らないよう教育しましょう。
そして散歩から帰ったら、目視と手で触ってマダニチェックもしましょう。毛の中にぽつぽつしたものや、ポコッとしたものがあれば要注意です!!
もしマダニが毛にひっついても、皮膚に食らいつく前ならブラッシングで排除もできます。散歩コースにどうしても草むらがあれば、コームで念入りにブラッシングしましょう。
特に耳や目、おしりのまわりなど、比較的毛の薄い場所はマダニが潜みやすいので丁寧にブラッシングします。
ブラッシングするときはなるべく外でしましょう。マダニが家の中に入って人を襲う可能性もあるからです。
月に一度の投薬でマダニ避けもできる!

マダニ予防のためには、犬を茂みや草むらに近づかせないことや、散歩から帰ったら必ずブラッシングしてマダニが付いていないかチェックするなどの生活習慣が欠かせません。
それと合わせて、月に1回の投薬もおすすめします。
私は、愛犬には背中にポタポタ落とす「スポットタイプ」の薬を使っていました。
最近は薬の種類が増えて、おやつタイプや味付きの錠剤(経口薬、チュアブルタイプ)などがあって、犬も人もお互いストレスなく簡単に薬を与えることができます。
しかし問題はアレルギーです。私の愛犬にはアレルギーがあり、市販の薬はアレルギー反応が起きないか心配で使えませんでした。
そんなとき、自宅から近い場所で信頼できる動物病院を見つけました。今は月に1回その動物病院へ通い、マダニ用の投薬をしてもらっています。
あなたの愛犬にもアレルギー持ち、あるいは錠剤を飲んでくれないなら、動物病院での投薬をおすすめします。
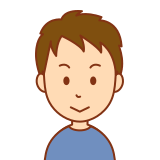
マダニの繁殖シーズンは4月〜10月だよね。
その間だけ投薬してもらって、それ以降は投薬しなくてもいいの?
マダニは特に気温が20℃~30℃、湿度70%が活動、繁殖がピークになる時期です。そのため、「4月〜10月」の春から秋に投薬はした方がいいですよね。
しかし、マダニは年中活動しており、冬だからといってマダニが出現しないわけではないのです。
冬も心配なら、1年を通してマダニの予防薬を投与しても大丈夫です。
まとめ

- マダニの取り方には線香が有効で、蚊取り線香でも代用ができる
- ライターやマッチの火を直接マダニに近づけるとヤケドのおそれがあるため、避けた方がいい
- 家庭内で吸血する「ツメダニ」は吸血したら離れるが、草むらや自然の中に生息する「マダニ」は一度噛んだら離れない
- 線香がなければ、塩、ワセリンを使った取り方もある
- 犬や猫などの動物にマダニが噛みついたら、酢水を使った取り方が有効
- 動物のマダニを取った後は、人間や他の動物に二次感染をしないよう、2週間くらい隔離した方がいい
- マダニに噛まれても気づきにくいため、特に動物は散歩の前後にマダニチェックをこまめにしてあげる
- こまめに見てあげられないなら、予防薬を投薬してあげるのもアリ
マダニに噛まれているのを発見したら、本当なら病院ですぐに取ってもらうべきです。
しかし病院で取ってもらうよりも一番重要なのは、「少しでも早く皮膚から離すこと」です。
いろんな取り方はあるものの、「人間なら線香や塩・ワセリンで取る」「犬などの動物なら酢水やワセリンで取る」のように時と場合に応じて使い分けましょう!
野外へ行く時には、「蚊取り線香」「調味料用の塩」「ワセリン」を必ず持っていけば、全部の方法を試せますね!
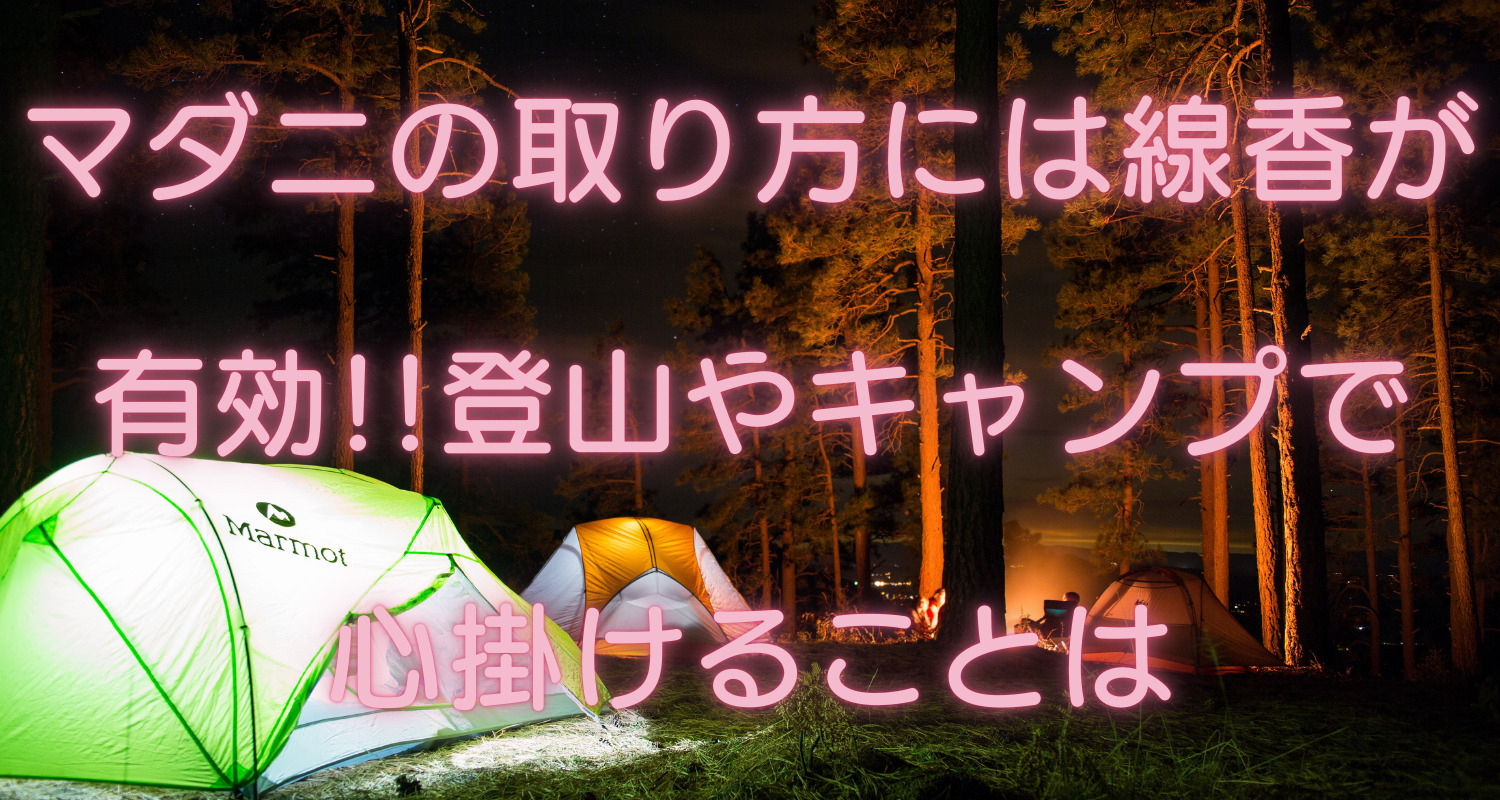
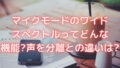
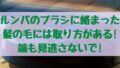
コメント