5歳になった子どもでも、ときどき抱っこを求めてきますよね。しかし、赤ちゃんとは違い体重が重いです。
ママは抱っこしてあげたいと思う反面、「重いから勘弁して〜」「肩も腰も限界…」と思ってしまいますよね。
私も子どもを育てていますが、0歳で既に長時間の抱っこは抱っこ紐がないとできません。
急な抱っこに対応できる補助グッズなら、子どものお尻を支えられるバッグがおすすめです。「ダッコリーノ」なら、5歳の平均体重20kgまで対応できますよ!
重い子どもを抱っこするのに役立つ抱っこの補助具、5歳になっても抱っこはしてもいいのか、抱っこを求める心理と対策を紹介します。
上手く抱っこ紐などを活用して子どもとのスキンシップを図りましょう♪
5歳の抱っこが重いならダッコリーノなどの補助具を使う

いつものお出かけのときや旅行に行ったときは、いつもの生活リズム通りに行動するのはとても難しいですよね。
5歳になって体力がついたとはいえ、環境が変わると刺激を受け疲れて抱っこを求めてきます。
まして5歳の子どもが寝てしまったら、重い荷物と化します。「ベビーカーもないし、抱っこしかないのか…。」と諦めて重いのを我慢しながら抱っこしますよね。
そんな時には、「ダッコリーノ」が大活躍します!これは、バッグが抱っこ紐に早変わりするものです。
抱っこの補助具としてはもちろん、バッグとして荷物もたくさん入るので人気です。
パパ向けのヒップバッグタイプだけでなく、ママ専用のおしゃれなダッコリーノも販売されています!耐荷重は20kgくらいですが、時期が過ぎたら普通のバッグとして、継続使用できます。
抱っこ紐は適齢期が過ぎると使えなくなりますが、バッグとしてずーっと長く使えるのはうれしいですね。おしゃれなバッグが抱っこの補助具なんて、他のママが見たら羨ましがられますよ♪
Gooseketの抱っこ紐なら軽くて持ち運び楽ちん♪
インスタグラムの広告などでたまに流れてくるGooseketの抱っこ紐は、世界50か国で愛されている抱っこ紐です。
腰が据わる6ヶ月〜体重20kgまで使えるので、セカンド抱っこ紐として優秀です。
この抱っこ紐は約230gで軽量です。使わないときは手の平サイズまで畳めるので、荷物がかさばりません。
そして、腕抱っこを再現していて密着しやすい設計のため、お子さんも安心できます。
使う人によって紐の長さを調節できるため、家族で共有して使えます!
カラー展開も豊富なので好きな色を選べるのも良いですよね♪「荷物はなるべく少なくしたい派」の私は購入検討中です!
抱っこは親ができなくなれば自然に卒業できる?
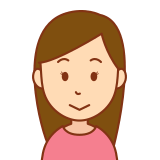
子どもはいつまで抱っこを求めてくるの?
だいたい小学校へ上がる前の、5歳か6歳で抱っこを卒業する子どもが多いです!その理由は、「重いので抱っこできなくなった」が多く挙げられます。
また、「恥ずかしいから」と外での抱っこをせがまなくなる子どももいるみたいです。
抱っこをするときは時と場所を選んだほうがいい
ですが、抱っこには場所を選ぶ必要があります。私の友人は抱っこをしたまま保育園へ登園すると、「抱っこで登園はやめて」と言われたそうです。
保育園や幼稚園によっては、年齢が大きい子どもは「子どもの自立を促すため」として、抱っこ登園はなしになっています。
抱っこ自体がダメというわけではなく、抱っこでの移動がダメということです。5歳になった子どもを抱っこするのは家の中など場所を選んだほうがいいですね。
5歳でも抱っこを要求して歩かないときの対処法!

5歳になって歩けるけど「抱っこ抱っこ…」で抱っこで歩かないと悩む親は多いです。
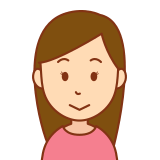
うちの子、ひどい場合は家を出たばかりなのに、すぐ座り込んじゃって歩かないのよ。
そんな時は、動いているものや目立つものに注目させるなど、子どもも楽しみながらできる「歩かせる工夫」をしましょう!
突然「抱っこしない!」などと子どもを突き放してしまうと、「えっ、ママに嫌われた?なんで!?」とビックリして、もっと歩かない子になってしまいます。
そんなときは、以下の方法を実践してみてください!
- 目の前にあるものを見て、しゃべり続ける
- 目標物まで一緒に歩く
- 子どもと競争しながら歩く
- 動物ごっこをしながら歩く
- 子どもに頼って、連れて行ってもらう
まずは、「そろそろ抱っこを求めてくるかな~」というタイミングで、少し先読みしてしゃべり続けましょう!
子どもと会話をすること自体が子どもの心理的な変化もつかみやすいので、おすすめの方法です。
「消防車があるよ!」「雲が大きいねえ」など、とにかく何か対象物を見つけながら話し続けます。それに気を取られると、そのまま歩き続けてくれます。
また、目的のものが近ければ、「あの信号まで行ってみようか」「あそこにあるお花はなんだろう!」などと話しかけ、とにかく目標物まで歩きます。
そこまで歩けて、まだ行けそうだったら「赤いポストまで行けたらカッコいいね!」など少し距離を伸ばしていきます。
行く先に自分の興味のあるものがあると自然と歩きます!ですが、ダメそうだったら押し付けないで無理させないようにしましょう。
そして、車が来ないような道なら、競争しながら進んでみるのもいい作戦です。
子どもはなりきることが大好きで、よく保育園のリトミックなどでも取り入れられています!気分を変えるのにもとても効果的です。
動物になりきって歩くなど、いつもと違うちょっと面白い歩き方をしてみると楽しんでノッてきますよ。
「子どもを頼る」については、子どもは大人に頼られるのがとても好きです。
「お願い、ママを〇〇まで連れて行って…」とお願いすると、5歳で自我が芽生えている子どもなら張りきって引き受けてくれます。
子どもが自分で選んだ靴を履けば喜んで歩いてくれる!
子どもに靴を選んで気に入ったものを身につけます。自分の好きなものは自然と自信になって、歩くのが楽しくなってきます。
また、「人に見せたい」などの心理が働いてウキウキな気分で歩いてくれます。
大人も同じで、自分の好きなものを身につけているときは自信がつきますよね。
ただ疲れやすい体質なら小児科に相談しよう
ただ、5歳になっても歩きたがらない背景として、疲れやすい病気や発達遅延などが考えられる場合もあります。
なにか気になる場合はかかりつけの小児科などで診てもらいましょう。
5歳で抱っこをせがむ理由は子どもによる!

5歳に成長しても子どもは抱っこをせがむのです。その理由は、以下が考えられます。
- 安心感を求めているから
- 甘えたいと思っている
- 抱っこでの移動が楽だと気がついた
- 高い視点から景色を見たい
多くの理由は「甘えたいと思っている」「安心感を求めている」ことが挙げられます。
こう思う背景には、下に兄弟ができた場合や、親が忙しくなったことで一緒にいる時間が減ってしまった場合などが考えられます。
また、このような状態だと「赤ちゃん返り」を起こすこともあるため、抱っこやおんぶが赤ちゃん返りの表れとして出るのですね。
そして、5歳のお子さんは意外と賢いものです。自分で歩かなくても抱っこをしてもらえれば目的地に着くのが楽だと、5歳ながら気づくのです。
大人と同じですね!子どもも楽な方法を選んでしまうということです。
さらに、子どもにとって見える視点とパパ・ママの視点は異なります。
それを抱っこしてもらった時に気づいているため、「もっと高いところから景色を見たい!」と思い、抱っこをせがむのです。
抱っこをしてもらうことでいつもとは違う景色を見渡せることができるのです。
抱っこやおんぶから見える景色は子どもにとって特別なものなんですね♪
子どもの甘え方は抱っこだけじゃない!
子どもの甘え方は子どもによってさまざまで、抱っこなどのスキンシップ以外にもあります!代表的な甘えは以下の内容です。
- 抱っこなどスキンシップをする
- しつこく「なんで?」と話しかけてくる
- ワガママを言う
- 思い通りにならないと、かんしゃくを起こす
- わざと「できない」と主張する
- 兄弟をいじめる
子どもが甘えてくる裏には安心感、心の整理や愛情の確認をしています。
家事などで忙しくて、「なかなか子どもに時間を取れない」というママも多いです。
子供の甘えに応えてあげられないと、いつもよりワガママが過激になったり、すぐ「できない」と諦めたりしてしまいます。
子どもが諦めてしまうと、親は「甘えてこないから楽になった」と一瞬ホッとしますよね。
ですが、今度は外で欲求を満たそうとしてしまいます。そのため、保育園や幼稚園で攻撃的になったり、ワガママを押し通そうとしたり、家以外で爆発してしまうのです。
なので、家事をする手を一旦止めて子どもと話したりスキンシップをとるか、子どもを甘えさせる時間を設けることで解消されていきます。
子どもは外で集団生活を送り、思い通りにいかないことも多少我慢してしまいます。家庭で親に甘えて、心のバランスをとっています。
それは、大人と同じですよね。私も外ではシャキシャキ働いていますが、休みの日は家でネット配信を見ながらグータラしています(笑)
子どもが甘えを求めてきたときには、子どもの心に寄り添いましょう!
「甘えさせる」と「甘やかす」は意味が違う!
「甘えさせる」ことに子どもにとって必要なことですが「甘やかす」こととは違います!
「甘やかす」とは、例えば大人がすぐに助ける、我慢しなくてはいけない場面で子どもの思い通りにことをすすめることです。
子どもを甘やかしすぎると、子どもの自己肯定感が育たずにワガママになってしまいます。
それに対し「甘えさせる」とは、子どもの気持ちを理解して心理的な欲求を満たすことです。
上手く甘えさせられると安心感が得られ、日本人が低いといわれている自己肯定感を育てることができます。
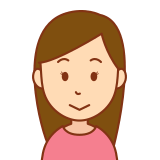
うちは5歳の子どもがいるけど、ワガママに育ってしまいそうだから抱っこを求めてきても応じないの。
よくこんなお母さんの「抱っこ=甘えている=ワガママになる」との考え方の家庭もあります。
ですが、その考え方は逆なのです。子どもが求めるときに甘やかしてあげないと、逆に子どもはワガママになってしまいます。
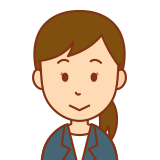
子どもの「甘えたい」サインは、見逃さないでください。
表情や行動のサインがないか、意識することから始めてましょう。
子どもの好きなこと、嫌なこと、楽しいことなど子ども自身を深く知りましょう!
そうすることで、子どもの「甘えたい」サインに気付くこともできるようになります。
まとめ

- 5歳の子どもを抱っこするとき、「ダッコリーノ」や「Gooseket」などの補助具を使うといい
- 抱っこは、親が「重いから無理」と意思表示をすれば、自然と子どもは要求しなくなる
- 抱っこ登校ができない保育園もある
- 抱っこを要求して歩かないときは、周りに子どもの注意を向けて一緒に歩くよう仕向ける
- 子供に好きな靴を履いてもらうと、自分から歩いてくれる
- 5歳で抱っこをせがむ理由は、「甘えたい」または「安心感を求めている」可能性が高い
- 特に自分がお兄ちゃんやお姉ちゃんになると、「赤ちゃん返り」をしてしまうこともある
- 自分が楽をしたいから、抱っこしたときの景色を見たいから抱っこをせがむこともある
- 甘えてくる時には、思いっきり甘えさせることが大事である
- 抱っこをたくさんしたからといって、ワガママに育ってしまうわけではない
子どもを抱っこやおんぶできる期間は、悲しいほどあっという間に過ぎてしまうものです。
5歳にもなると重いからツラいかもしれませんが、抱っこできるのは今だけです!子どもは成長して自分で行動ができるようになるにつれ、自然と親から離れていきます。
「あの頃はかわいかったのに、いつの間にか甘えなくなっちゃった」と後悔しないよう、今のうちにたくさん甘えさせましょう。今しか作れない思い出をたくさん作ってくださいね
また、来年には6歳を迎えるなら一人で寝てもらえるようにも訓練しておきましょう!詳しくは、こちらの記事で紹介しています。
寝かしつけはいつまでも続けず6歳で卒業?先輩ママ達の一人寝対策とは



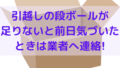
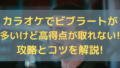
コメント