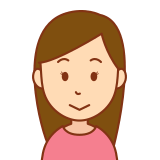
今度5歳の誕生日に、「ニンテンドースイッチ買って!」って言われてるの。
お友達がもう持っているらしいんだけど、まだ早いよね…。
ゲームに興味があるのは悪いことではありませんし、家族の誰かが持っていたら貸してあげてもいいですよね。
しかしだんだん不自由に感じたら、このように「自分のが欲しい!」とせがみます。
私がゲームを始めたのは12歳で、弟や家族と共用でした。それなのに5歳で自分専用が欲しいとは…もはや世代が違いますね。
ところが、「5歳は早いかもしれないけど、家庭内のルールが守れるのなら買ってあげてもいい」という家庭が意外にも多いのです。
話を聞いていくと、5歳の早いうちだからこそメリットもあるのです。今回はおすすめソフトも交えて解説します。
ニンテンドースイッチが5歳には早い…むしろ適齢期?
ニンテンドースイッチ(Nintendo Switch)は、意外にも5歳から使い始める家庭が多いです。
「まだ早いかも。」と心配になりそうですが、「ゲームに熱中しすぎず、家庭のルールを守れるのなら買い与えてもいいのでは。」と思う親御さんも多いです。
5歳のうちから欲しがるということは、ゲームに興味を持っているのです。
それにお友達がswitchの話をしていたり、家族のswitchを借りてプレイさせてもらったり、生活の中にswitchの話題が入ってきたら、おのずと興味がわいてきます。
ニンテンドースイッチには、5歳でも遊べるソフトが販売されています。
5歳でもまだゲームに興味を示さないのならまだ早いかもしれませんが、すでに欲しがっているのなら適齢期なのです。
ニンテンドースイッチは主に個人プレイのゲーム機
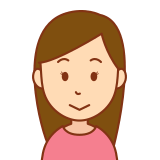
ニンテンドースイッチって、私も夫も持ってるんだよね。
一家に同じゲーム機が2台も3台も必要ないんじゃないかな?
親がswitchを持っていれば、時間を決めて貸してあげることも可能です。
しかし、ニンテンドースイッチは主に一人プレイ用です。そのため、ソフトの内容にもよりますが、セーブ機能が一人分しかついていないソフトもあります。
たとえば、大人気ゲーム「あつまれ どうぶつの森(通称 あつ森)」というソフトは、無人島へ移住して、自分だけの島を一から作り上げるゲームです。
この島は、switch1台ごとに一つしか作れません。親のswitchを借りてプレイした場合、親の島を借りることになります。
もしお子さんが「自分だったらお花がいっぱいの島を作りたい!」と思っても、新しい島を作るにはswitchをもう一台買わないといけないのです。
このように、親が積み重ねたスコアや記録の中でしか遊べないと、自由度が低く感じられるのです。
実は私、「スーパーファミコン」「PlayStation2」のようなテレビゲームでしか遊んだことがありません…。
これらは「一家に一台」という認識で、ゲームソフトによっては家族で一台のゲーム機をシェアするためにセーブ機能が複数ついていました。
「あつ森」に例えるなら、一台のゲーム機で複数の島を作れる、ということです。
もはや、「一家に一台」でシェアする時代から、「一人一台」で所有する時代に変わったのですね。私の認識はだいぶ古いようです(笑)
親の話を素直に聞けるうちからゲームに触れる
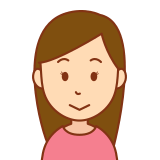
私が子供の時、10歳くらいに初めてゲーム機を買ってもらったのよね。
周りのお友達は5歳くらいなのに、もう買ってもらっているの?
5歳のうちは、まだ親との関係性が親密で、親からの注意やお願いを素直に聞いてくれる時期です。
そんな今のうちに、親が決めたルールや話を素直に聞いてもらいつつ、ゲームとの付き合い方を学ぶのです。
子供は、小学生になると自我が発達し、中学生になると反抗期を迎えます。
成長するにつれて、親と過ごすよりも友達と過ごすほうが楽しくなります。そのため、だんだん親の言葉が届かなくなってしまうのです。
親の言葉が届く今だからこそ、ゲームとの付き合い方を学び始める時期でもあるのです。
かといって、たくさんのゲームをプレイさせるのではありません。お子さんが興味ありそうなソフトだけをインストールして、限られた範囲内で遊んでもらうのです。
早いうちからゲームに慣れておけば、時間を忘れてのめりこむほど熱中しすぎず、大人になっても適度にゲームを楽しめます。
テレビモードは大画面で遊べて監視しやすい
ニンテンドースイッチには、遊び方が3種類あります。その中で、家庭でよく使われている遊び方は「テレビモード」です。
ジョイコン(Joy-Con)と本体を合体させる「携帯モード」、本体をテーブルに置いてジョイコンを持って遊ぶ「テーブルモード」は、本体が画面ディスプレイになります。
しかしこの本体は、通常版なら6.2インチ、有機ELモデルなら7.0インチです。ちなみに比較するなら、iPhone(最大6.7インチ)が同じくらいの大きさです。
iPhoneくらいの画面だと家事をしながら様子を見るには画面が小さくて、今どんなゲームをしているか監視が難しいです。
そこで、本体とテレビを接続して「テレビモード」にすれば、他モードよりも画面ディスプレイが大きくなります。
少し離れたところで家事をしていても、テレビ画面にゲームの様子が映し出されて監視しやすくなるのです。
それに、お子さんも離れたところから遊んでくれるため、視力低下も防げます。
ちなみに、Nintendo switch liteは携帯モードでしか遊べません。そのため、ちょっと高くても通常版を選ぶ人もいるのです。
みまもり設定であらゆる制限をかけられる
ニンテンドースイッチは、お子さんのゲームプレイに制限を付ける「みまもり設定」が備わっています。
みまもり設定では、主に「ゲームのプレイ時間」「第三者とのやりとり」「課金購入」を制限します。
子供にプレゼントする前に、あらかじめ親がスマートフォンアプリやニンテンドーアカウント設定にて登録しておきます。
ゲームのプレイ時間を設定しておけば、その時間が近づいたときにアラームで知らせてくれます。たとえ熱中していても、時間オーバーしにくくなりますよ。
家庭によっては、あえて見守り設定を使わず、子供に時計を見て時間の管理をさせている人もいます。
「時計の長い針が12に来たらやめようね。」「今長い針がどこに来ているかな?」などと声をかけておけば、自然と時計の見方も覚えられます。なかなか高度テクニックですね!
また、第三者とのやりとりやコミュニケーションを制限しておけば、インターネットを通じて人間関係のトラブルや事件からお子さんを守れます。
そして、お子さんが誤ってボタンを押して課金してしまうこともないため、余計な出費の不安もなくなります。
私も、過去にはゲームに熱中しすぎてついつい課金をしてしまい、気が付けば1万円分を課金してしまったことがあります。
1回の課金が少なかったとしても、回数が積み重なれば金額も大きく膨れ上がります。「ちりも積もれば山となる」ってやつですね。
最低限のルールを決め、罰則も話し合う
そのためにも、遊び始める前に「これだけは守ってほしい!」というルールを2~3個程度ピックアップして決めて、子供と相談して決めます。
親側もルールを吟味しておけば、ゲームを楽しむことよりもルールを守らせることが目的になったり、後からルール変更になったり、子供とケンカの種がなくなります。
では、家庭でよくあるルールを紹介します。
- ゲームをする前に、その日やるべきことを済ませる(生活習慣、宿題、習い事など)
- 時間を守る
- テレビモードで遊ぶ
- 外に持ち出さない
- ルールが守れなかったときのことを決める
5歳の幼稚園児にとって「その日やること」といえば、手洗いやお手伝いのような、生活習慣です。
しかしその1~2年後、6歳になって小学校に入学すると、「宿題」が待っています。ピアノやスポーツ教室に通っていれば、習い事の練習もしなくてはなりません。
今はまだ幼稚園にしか通っていなくて遊ぶ時間が多くても、年齢があがると、勉強や塾、習い事など、やるべきことが増えていきます。
やるべきことが少ない5歳のうちに「まずやるべきことをやる」と習慣付けることで、失敗を繰り返しながら、勉強と遊びの両立がうまくなるのです。
そして、長時間プレイさせないためにも、ゲームの時間を決める家庭も多いです。
休日に時間を持て余しているなら、「平日は1日30分、休日は1時間」のように、休日を多めに設けてもいいです。
家庭によっては、「疲れたら自分でやめるから、ゲーム時間を特に決めていない」「時間が多少過ぎても、キリがいいところまで遊ばせる」として、子供に気遣いをしています。
ちなみに、就寝前の1~2時間前にはゲームを終わらせたほうがいいですよ。
光が強い画面にて脳が活性化して眠れなくなると、学校や幼稚園で居眠りをして、先生に注意されてしまいます。
もう一つ、まだ一人で物の管理ができないのなら、ゲーム機の持ち出しも避けましょう。親戚が集まるときだけ特別に持ち出して、一緒に管理するのはアリですね。
最後に、ルールが守れなかった時のことも話しておきます。
ちなみに私が子供のころは、「ゲームの前に宿題を終わらせる」「ゲームは1日1時間まで」というルールでした。
ルールを破ると「ゲーム禁止」を言い渡されました。期間は長くても1カ月くらいでしたね。
この間はつまらなかったですが、友達や弟と遊んだり、親のお手伝いをしたり、改めて身近な人と向き合う期間になりました。
お子さんのことを考えてあれこれルールを決めたい気持ちもわかります。
「せめてこれだけは守ってね」と話し合っておくと、お子さんもルールに縛られず、自由時間を楽しめます。
ニンテンドースイッチで5歳におすすめソフト
5歳のお子さんが初めてニンテンドースイッチに触れるなら、まずは興味を持ってもらい、楽しく操作してほしいですね。
操作を覚えるためにも、お子さんが興味のあるソフトの中から、操作が簡単そうなソフトを選びましょう。
中でも大人から子供にまで人気がある「マリオパーティ」は、主にミニゲームで構成されていて、操作もシンプルです。
最初は慣れなくても、ジョイコンの使い方も覚えて、だんだんボタン操作がスムーズになります。
ただし、ちょっと難しそうなソフトでも、お子さんのやる気が強ければ購入してあげてもいいと思います。
「好きこそものの上手なれ」という言葉があるように、好きなことにはとことん打ち込みますよね。
そのため上達も早く、夢中になったら親をも追い越します。
私だったら、「うちの子まだ5歳なのに…天才じゃね?」と、親バカを発揮しそうです(笑)
また、今は特にソフトへの興味がないなら、遊びながら文字や数字を学べる「知育ソフト」もおすすめですよ。
「ドラえもん」「アンパンマン」などのキャラクター系知育ソフトなら、就学前の勉強も楽しくなります。
慣れてきたら人気タイトルにも挑戦
操作に慣れてきたら、少し操作性が高い人気ソフトにも挑戦してみましょう。
大人から子供でも人気が高い、代表的なゲーム作品を紹介します。
- スーパーマリオシリーズ
マリオカート
プリンセスピーチ - ポケットモンスター(ポケモン)
- 星のカービィ
- ピクミン
- あつまれ どうぶつの森(あつ森)
- MINECRAFT(マインクラフト、マイクラ)
- スプラトゥーン
- スマッシュブラザーズ(スマブラ)
先ほど「マリオパーティ」も出てきましたが、「スーパーマリオシリーズ」は任天堂の代表的なゲームです。
「マリオカート」は難しそうですが、補助機能を付ければコースアウトせずに完走できます。
自分で操作できる感覚を身に着けさせて、慣れてきたら補助機能を外せば、自信もつきますよ。
「ポケモン」「カービィ」など、人気キャラクターのゲームもお子さんの興味を引き付けます。
また、最初に例として紹介した「あつ森」は、他キャラクターと触れ合うことで、コミュニケーション能力なども身に付きます。
さらに難易度が高くなると、バトル性の高い「マイクラ」「スプラトゥーン」「スマブラ」も操作できます。
「マイクラ」では、ゲームをしながら自然とプログラミングを学べます。
バトル性が高くなると、相手から攻撃されたときにかわしたり、防御したり、とっさの瞬発力や判断力などが必要です。
私も、YouTuberのスマブラ実況を見たことがあります。
コントローラーをずっとカチャカチャやっていて、「早すぎる、私には無理だ…。」と圧倒されました。
こんなスマブラ操作を5歳ができるとしたら、もし私なら親戚に自慢するかもしれません(笑)
運動不足解消には、体を使って遊ぶソフト
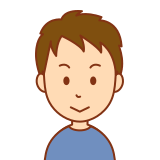
家の中でゲームばかりしていると、運動不足になるんじゃないかな?
心配には及びません、体を使って遊ぶソフトもありますよ。
「リングフィットアドベンチャー」は、フィットネスと融合させた新感覚ゲームです。
別売りのリングコンとレッグバンドを準備して、エクササイズやヨガをしながら操作します。
「Nintendo Switch Sports」では、家の中で様々なスポーツが楽しめます。
雨が降っていて外で遊べない時でも、これらなら運動不足の解消になります。
全年齢対象(CERO A)のソフトを選ぶ
ゲームソフトには、箱や説明書に必ず対象年齢が明記されています。これを「CEROレーティングマーク」といいます。
5歳くらいに適しているのは、全年齢対象(CERO A)です。
全年齢対象のソフトには、不適切な内容や、大人的な要素が含まれていません。
大人の悪い影響にさらされず、子供の世界だけで楽しめるのです。
ちなみに、全年齢対象の一つ上は「12歳以上対象(CERO B)」です。
中学生にあがるまでは、平和的で健全なゲームソフトで遊んでもらいましょう。
ゲームによっては考える力や知識が身につく
ゲームはただ遊ぶだけのものではありません。遊びながら、ゲームの操作性や健全な発達も促せます。
- 自分で考える力が身につく
- 判断力、瞬発力、記憶力がよくなる
- 手先が器用になる
- 自然と文字を覚える
- 専門的な知識も身につく
- コミュニケーション能力、社会性が発達する
まず、ゲームを攻略するには「考える力」が必須になります。
どうすればこのゲームをクリアできるのか、自分で考えて操作することで、自頭が鍛えられます。
また、とっさの判断力や瞬発力により手先も器用になっていきます。
それだけでなく、ゲーム用語やキャラクターの名前なども覚えるため、記憶力がよくなります。
自然とひらがなやカタカナも覚えますし、ソフトによってはプログラミングや英語、音楽も学べます。
そして、登場人物と触れ合うことでコミュニケーション能力も身に付きます。
お金を扱うゲームでは、買い物のルールも身に付きます。慣れてきたら、簡単なおつかいも任せられますよ。
「知育ソフト」ではなくても、適度なゲームそのものが「知育」になるのですね。
ニンテンドースイッチで5歳女の子におすすめソフト
ニンテンドースイッチには、このような女の子用のソフトもあります。
- ゆるキャラ
- ディズニー
- アイドル、プリンセスもの
キャラクターゲームの中でも、5歳女の子には、ゆるキャラや動物あたりが好まれます。
また、ディズニーは王道ですね。特に「ツムツム」はかわいいキャラクターが多くて、目移りしそうです。
それに、アイドルやプリンセスは女の子のあこがれでもあります。
お洋服の着せ替えやメイクも、ちょっとお姉さんになった気分で楽しめます。
私が5歳のころにも、着せ替え人形で遊んでいましたよ。いつの時代も、女の子は着せ替えが好きなんですね♪
まとめ
- 子供がニンテンドースイッチを欲しがっているなら、5歳であっても適齢期である
- ニンテンドースイッチは、本来携帯型ゲームでソロプレイ用なので、セーブデータも一人用しかついていない
- 小学生や中学生のように、自我や反抗心が芽生えたころよりも、素直な5歳児のほうが親の話を聞いてもらいやすい
- テレビモードで遊んでもらえれば、画面が大きくなって様子を見やすい
- 時間や課金などは、「みまもり設定」で管理できる
- ゲームを始める前に、子供と相談して2~3個ルールを決める
- 最初は操作が簡単なソフトをおすすめするが、子供が興味あるなら多少難しくてもいい
- 慣れてきたら、人気タイトルや難しいゲームに挑戦してもいい
- 大人の悪い影響を与えないためにも、全年齢対象(CERO A)のソフトを選ぶ
すでに「Nintendo Switch 2」も発売されていますが、持っている人はまだまだ少ないです。
保護者がきちんと管理すれば、知能や発達ツールにも、お友達と遊ぶきっかけにもなります。
たまには一緒に遊んで、親子の関係性もはぐくみながら、ゲームとの正しい付き合い方を教えてあげましょう。

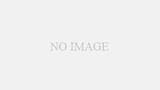
コメント