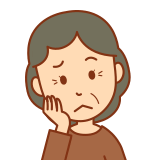
孫が近くの川で拾ってきた石なんですけど、何の石か知りたいらしいんです。
私には「ただの石ころ」にしか見えないんですけど…。
過去に天然石ショップで働いていたとき、こんなご相談を受けたことがありました。
店舗で販売している天然石は装飾品として加工されているため見分け方はわかりますが、拾ってきた石の種類までは特定しきれません…私も困りました。
このときは、知識不足を反省しつつ、丁重にお断りしました。しかし、このような石にもきちんと種類や見分け方もあるのです!
今回は、石の種類や特徴、見分け方だけでなく、石の成り立ちについても解説します。
石の種類には見分け方がある!
石全般のなかでも、ダイヤモンドや宝石のように一粒の結晶は「鉱物」、複数の鉱物やガラスが一つに組み合わさった石は「岩石」と呼びます。
一粒の結晶とは言えないようなまだら模様、または粒が混ざったような石は、今回「岩石」としてお話しします。
見分けるには、石の状態や拾った場所などを総合的に判断します。
岩石の種類は、大きく分けて3種類です。最初に、簡単な火成岩と堆積岩の見分け方を説明します。
- 火成岩の場合
拾った場所の近くに火山があるか
火山(マグマ)由来の結晶や鉱物が含まれるか - 堆積岩の場合
石が見つかった近くで、粒子が水や風などで運ばれた形跡が残っているか
粒子の大きさがそろっているか
まず、火山から成り立った岩石は「火成岩」といいます。漢字も、「火から成る岩」と書きますね。
火山内部のマグマが噴火、あるいは火山ガスとともに山の斜面を下った(火砕流)ことで地上へ出てきて、そのまま冷えて固まったのです。
そのため、石を拾った場所の近くに火山がある場合、そして粒が角ばっていれば、火成岩の可能性が高いです。
ちなみに、その火山周辺にどんな鉱物が多いか、またどんな鉱物が少ないかを知っておけば、岩石の種類も絞り込めますよ。
つぎに、何かが積みあがって、長い年月圧縮されて固まった岩石を「堆積岩」といいます。
積みあがったものは、岩石の破片(泥や砂、粒の直径が2mm以上の礫(れき))をはじめ、サンゴや貝殻、植物の破片、火山灰など、様々です。
何が積みあがったかは、その場所によります。
海の近くで昔はサンゴ礁が広がっていた場所なら、サンゴの化石が堆積した「石灰岩」の可能性が高いです。
また、近くに火山があるのに、石の粒子が細かくて火成岩っぽくなければ、火山灰が堆積した「凝灰岩」の可能性も出てきます。
モノが構成されたときには、何か理由があるハズです。
その土地の歴史や環境にも目を向けて、岩石が出来上がった時代背景まで見えれば、石のロマンをより深く感じられますよ。
火成岩は結晶の大きさや色で見分ける
火成岩は、火山のどの部分で出来上がったのかによって結晶や粒子の大きさで、「深成岩」「火山岩」の二種類に区分されます。
肉眼でハッキリと結晶の粒がわかりやすい場合は「深成岩」、肉眼で見分けられないほどの細かい結晶も含む場合は「火山岩」と呼ばれます。
この違いは、結晶の大きさ、マグマのどの部分で作られたのかによります。
「深成岩」は、漢字で「深いところで成り立った岩」と書きますね。その字のごとく、結晶が火山深くでじっくりと大きく成長した岩なのです。
火山の地下深くでマグマがゆっくり冷えて固まると、肉眼で確認できるくらいまで結晶の粒が大きくなります。
ちまみに、この結晶を「斑晶」、斑晶が集合している状態を「等粒状組織」といいます。
「年月をかけて出来上がった岩石」と聞くと、ロマンを感じますね。
対して、火山岩は肉眼ではハッキリ見えないくらいの細かい結晶も集合しています。
このような細かい結晶はマグマが急激に冷えて固まった部分で、「石基」と呼ばれます。どちらかというとガラス質な成分が多いです。
マグマは、地下深くだと温度が高く、地表に近くなると温度が低いです。深成岩とは反対に、低い温度で急激に冷えると結晶は小さくなります。
火山の噴火や地表近くまで押し上げられる現象により、地表近くに現れて温度が急激に冷えたため、結晶が細かいまま岩石として固まるのです。
このとき、地下深くで結晶化した鉱物が一緒に固まった場合、一つの岩石に大きな結晶と細かい結晶が入り混じることもあります。
〈深成岩をさらに見分けるなら…〉
「深成岩」は、石英と他鉱物との割合から、さらに「花崗岩」「はんれい岩」「閃緑岩」の3種類の岩石名まで特定できます。
専門家の人は、偏光顕微鏡や分析装置などで鉱物の種類を調べて、岩石の種類を特定します。
ただし野外に出ていると顕微鏡などは使えません。その場合、以下のように岩石の色味を比べてざっくり見分けます。
- 花崗岩…石英を多く含み、白っぽい
- はんれい岩(斑糲岩)…黒っぽい
- 閃緑岩…白と黒が入り混じっている
深成岩のうち、「花崗岩」が一番見分けやすいです。
花崗岩は、「無色鉱物」の斜長石、カリ長石、石英と、「有色鉱物の黒雲母の鉱物4種から成り立ちます。。
ここでは多く語りませんが、火成岩から主に産出される鉱物8種のうち、色が付いた鉱物(有色鉱物)は4種類あります。
つまり、黒雲母やその他の有色鉱物を多く含むと、「閃緑岩」「はんれい岩」と呼び名が変わるのです。
〈火山岩をさらに見分けるなら…〉
火山岩をさらに区別する場合、鉱物に関する知識を必要とします。
鉱物一つ一つの見分け方は難しいので説明しきれませんが、割合によって岩石名がこのように変わります。
- 流紋岩…黒雲母を多く含む
- 安山岩…輝石を多く含む
- 玄武岩…かんらん石を多く含む
- デイサイト…角閃石を多く含む
- 黒曜岩…天然ガラス
黒溶岩以外はとてもよく似日本で一番よくみられる火山岩は、「安山岩」です。
輝石とかんらん石を含んでいれば「玄武岩」、輝石が少なく黒雲母を多く含んでいれば「流紋岩」となるのです。
「デイサイト」はあまり見かけないマイナーな石です。みつけられたらラッキーですよ。
そして、なかでも見た目が異なるのは「黒曜岩」です。
これはマグマの中でガラスや珪砂がゆっくり溶けて結晶化したもので、岩石というよりは黒いガラスのように見えます。
切り口が鋭いため、昔の人は弓矢の矢じりなどに使っていました。
ジブリ映画の作品でも、黒曜石のペンダントが出てきます。現代とは異なる世界観だったため、古代から愛された石のひとつなのでしょうね。
堆積岩は粒の大きさや質で見分ける
堆積岩は、日本では岩石の破片、生物の破片、火山灰が堆積した場合が多いです。種類ごとにみていきましょう。
- 砕屑岩(さいせつがん)
岩石の破片が堆積して固まった岩石
泥岩、砂岩、礫岩など - 生物岩
生物や植物の破片が堆積してできた岩石
石灰岩、チャート、石炭など - 火山砕屑岩
火山の噴火で出てきた粒子が堆積して固まった岩石
凝灰岩(ぎょうかいがん)など - 化学的沈殿岩
水から結晶が沈殿してできた岩石
岩塩など
一番見分けがつきやすいのは、粒子の細かさで見分けられる砕屑岩です。
粉よりも粒子が細かければ「泥岩」、粉のように肉眼で粒子を見つけられれば「砂岩」、粒子が2mm以上ではっきり見えれば「礫岩(れきがん)」と呼べます。
生物岩の場合、例えば石灰質のサンゴや貝殻が堆積したものは、「石灰岩」になります。
そして「チャート」は石英の成分を含んでいて、鉄よりも硬いです。もっと詳しく話すと、「生物起源チャート」「非生物起源チャート」の二種類があります。
「生物起源」は海に住むプランクトン(主に放散虫)の殻や魚などの骨が堆積したものです。放散虫の殻はガラス質でとても硬く、成分が石英と似ています。
「非生物起源」は、熱水活動にてシリカ(石英の成分)が堆積したものです。
石英は、鉱物の中でも硬い種類のひとつです。この硬さを利用して、昔の人はチャートを刃物や武器に利用していたくらいです。
ちなみに、どちらの起源も海が関連しているため、チャートは海に近いところからよく発見されます。
また、動力エネルギーにも使われる「石炭」は、数千万年以上前の植物によるものです。
地中の熱や圧力によって植物の水分や酸素がなくなり、残った炭素のみが堆積したのです。
そして、日本ではあまり発掘されませんが、海外でよく採掘される岩塩も、海水の塩が固まってできた堆積岩のひとつです。
一番見分け方が難しいのは変成岩
岩石の3種類には、もう1つ、火成岩や堆積岩の質が変化した岩石「変成岩」があります。
明らかに他の2種類とは質が違う部分を見つけなければならないため、石の専門家でも見分けが難しいです。
変成岩の成り立ちは複雑で、すでに出来上がった岩石が、地殻変動などで地下深くへ取り込まれて構造が変化します。
高温の地熱によって鉱物同士が溶けて混ざりあったり、高圧に押しつぶされて硬くなったり、長い年月をかけて大自然の力を受け続けます。
そして出てきたときには、キラキラしていたり、縞模様になっていたり、他の岩石とはちょっと見た目が変わります。新たな岩石に生まれ変わるみたいですね。
変成岩は、地下の広範囲で形成される「広域変成岩」、深成岩の熱に触れた部分だけが変化する「接触変成岩」の二種類があります。
- 広域変成岩
火成岩や堆積岩が地下深くに引き込まれて、高圧や高温にさらされて変化する
縞模様になることが多い
結晶片岩、片麻岩など - 接触変成岩
主に、堆積岩が深成岩の熱に触れて変化する
高圧にはさらされないため、縞模様にはなりにくい
変成岩を見分けるには、岩石のどこが変質しているのか、内部の鉱物を顕微鏡でじっくり調べて判別します。
しかし、火成岩や堆積岩の知識が身に付いていないと、変質にも気が付きにくいです。
変成岩は縞模様になっていることが多いものの、火成岩や堆積岩にも縞模様状の種類はあります。
そのため、素人レベルではもちろんのこと、地学の専門的な知識を身に付けた人でも、変成岩の判別は難しいです。
石 種類 調べる方法
火成岩は主に2種類で、しかも肉眼で粒(結晶)が見えれば判別しやすいため、見分けやすいです。
しかし、堆積岩や変成岩は肉眼だけでは見分けが難しいです。堆積岩の種類が多いこと、変成岩は石の知識がなければ変化に気づきにくいためです。
しかし、石の特徴に合わせて調べれば、簡単に見極められますよ。例を一部あげましょう。
- 三角形や四角形などの形をした粒があるか(肉眼で粒がハッキリ見える場合)
- 釘で傷がつくか
- 塩酸と反応させる
- 縞模様があるか
まず、肉眼で粒がハッキリ見える場合、火成岩だけでなく、砂岩、礫岩のように、粒が肉眼でも見えやすい堆積岩の可能性もあります。
この場合、粒の形を観察します。三角形や四角形、六角形、柱状の粒があれば鉱物の結晶である証拠なので、「火成岩」に分類されます。
もしこのような粒がなければ、火山由来の鉱物は含まれていないため、「堆積岩」に分類されます。
あとはそれぞれ粒の大きさを観察し、火成岩なら粒の形がそろっているか、堆積岩なら2mm以上の粒が多いかどうかで見極めます。
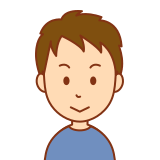
火成岩と粒が大きい堆積岩は、鉱物の結晶で見分けるんだね!
他の堆積岩や変成岩は粒が見えないけど、どうするの?
粒が見えない石は、チャート、泥岩、変成岩、石灰岩など、考えられる種類がたくさんあります。
釘で傷をつけた場合、ほとんどの石は傷がつきますが、チャートだけは鉄よりも硬いため、石に傷はつかないのです。
また、直接塩酸を石にかければ、石灰岩なら塩酸と反応して泡が出ます。
紙やすりで削る
肉眼で粒や結晶を観察するのが難しい場合、表面を紙ヤスリで削ったり磨いたりしてみるのもいいですよ。
火成岩は堆積岩よりも硬いです。そのため火成岩は表面に光沢が出てツルツルしますし、堆積岩は表面が削れたりザラザラしたり、石によって変化が見られます。
チャートは火成岩よりも硬いため削れず、逆に紙ヤスリの方が負けてボロボロになります。
紙ヤスリを使うときは、目の粗いものから細かいものへ順番に使用します。
この結果をもとに粒の形や大きさを観察すると、目が悪いお子さんでも石の種類を分類できますよ。
石の色はあくまでも参考程度にする
調べると、石の画像がたくさん出てきますよね。「黒っぽい」「白っぽい」などの大まかな特徴はありますが、必ずしも同じ色とは限りません。
私も、「白っぽい石は石灰岩かチャート」だと思っていました。しかし石に関するサイトを色々調べてみると、白っぽい泥岩もありました。
目に見える部分だけを観察しすぎると、先入観にとらわれて新しい発見を見逃してしまいます。
石にも個性があるように、色や形は様々です。見た目だけに惑わされず、石の性質を見て判断しましょう。
まとめ
- 石の種類を見分けるには、表面から見える粒の大きさや形、または粒が水や風などで運ばれた可能性を探す
- 表面の粒が三角形や四角形など、肉眼でハッキリ見えるなら「火成岩」である
- さらに、粒が大きめなら「深成岩」、細かい粒も含まれるなら「火山岩」に区分できる
- 同じような粒がそろっていれば「堆積岩」である
- 堆積岩の中でも、表面の粒が角ばっておらず形がそろっているなら、粒が小さい順に「泥岩」「砂岩」「礫岩」に区分できる
- 堆積岩は、その他にも生物や植物の破片による「石灰岩」「チャート」「石炭」、火山から出てきた粒子による「凝灰岩」などもある
- 火成岩や堆積岩に縞模様ができていたり、見慣れない鉱物が含まれていたり、変化が見られれば「変成岩」の可能性もある
- 石の種類は、釘で傷をつけて硬さを調べる方法、塩酸をかけて調べる方法もある
- 紙ヤスリをかけると、石の硬さを見比べながら調べられる

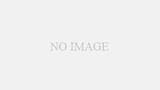
コメント