子供用の服や普段着を作るとき、手芸用品店で布を買いに行きますよね。しかし、手芸用品店ではたくさんの布を取り扱っています。
私もインテリア用に大きな布を買いに行ったとき、種類がありすぎてすごく迷いました。結局お目当ての布を見つけるのに1時間くらいかかったのです。
大きな幅を選んでしまうと、使うはずの布面積よりもハギレが多く出てしまい、生地ロスになります。かといって小さな幅を選ぶと、型紙が取りにくくなります。
布には、ざっくり分けて3種類の規格を設けています。
生地の用途や素材も分かれているので、何を作りたいか、どんな布地がいいかを規格と照らし合わせながら選びましょう。
今回は、布の様々な規格と、布を少し多めに買っておくべき理由を解説します。
布の幅には規格が用途別に3種類ある!
布幅は、お店によってばらつきはあるものの、規格が3種類に分けられます。
小物の裁縫用なら小さめのシングル丈、普段着や洋服用なら普通丈、外出着やよそ行き用ならダブル丈、などと用途に合わせて幅や素材が変わります。
- シングル幅(ヤール幅)…約90~92cm
お店では45cmくらいの幅で巻かれている
「S巾」「S幅」と表記されていることもある
素材…薄手な布(ブロード、シルク、レースなど)
用途…ベビー服や子供服、小物など - 普通幅(広幅)…約110~120cm
お店では55~60cmくらいの幅で巻かれている
素材…コットン、麻、化学繊維、プリント生地
用途…普段着や洋服など - ダブル幅(ワイド幅)…140~180cm
お店では70~90cmくらいの幅で巻かれている
「W巾」「W幅」と表記されていることもある
素材…厚手な布(ウールやニットなど)
用途…インテリアグッズ、アウターやスーツなど
シングル幅や普通幅は、10cm差なのはわかります。しかしダブル幅は、同じ規格なのに140cm~180cmまで、40cmも差があるんですね!
メーカーによっては、1ヤード幅(91~92cmくらい)だと「ヤール幅」、約110cmだと「広幅」のように、規格名が異なる場合もあります。
ちなみに、手芸用品店では、布を半分に折って巻いた状態で販売されています。
ダブル幅を半分に折ると、長いものでは90cmくらいになります。幅の長さはシングル丈90cmくらいと変わりませんが、素材が明らかにダブル幅用の厚手な布です。
「シングル丈は90cmだから!」と間違えてダブル丈を買ってしまうと、大きな予算オーバーはもちろん、本来作りたかったはずの作品とは違うものが出来上がってしまいます。
布が分厚かったり、二つ折りになっていたり、本来買う予定だった布とイメージが違っていたら、店員さんに確認してみましょう。
布業界のルールに沿って規格と金額を統一している
生地の幅は、布業界のルールによって統一しています。これは、布の価格を定めるためや、扱いやすくするためでもあるのです。
布を作るメーカー側が、自分たちで幅を決めて自由に作っていると、1mあたりの布の値段がバラバラになります。
すると、販売するお店側がこんがらがりますし、布を買う人達も「どっちが安いの?」と頭を悩ませてしまいます。
そこで、生地の幅を3種類にざっくり統一することで、お店側も布を買う人達も選びやすくなるのです。
これは、「拡大質問と限定質問」の話によく似ています。
たとえば、「今日の晩ご飯、何がいい?」と聞かれるとイメージしにくいですよね。私が聞かれても、つい「何でもいいよ。」と言いそうになってしまいます。
しかし、「今日の晩ご飯、からあげと魚の塩焼き、どっちがいい?」のように選択肢を限定すると、人は選びやすくなります。
また、「魚は食べたいんだけど塩焼きって気分じゃないな、刺身がいいかな。」などと、新しい答えも出てきます。
布の場合も、たくさん種類がある中から1種類を選ぼうとすると、迷ってしまいますよね。
そこで、「子供服や小物を作りたいとき」「大人用の洋服を作るとき」「スーツを仕立てるとき」のように、目的と必要な布面積をに応じて幅の規格を分けているんですね。
生地の素材や厚みもだいたい決まっていれば、お店の中であれこれ迷わずにスムーズに決められますね。
生地ロスを減らしたいならシングルか普通を選ぶ
せっかく布を買うなら、なるべく短い布面積で、はぎれが出ないようにしたいですよね。
生地ロスを少しでも減らしたいなら、幅は狭い方を選びましょう。しかし、型紙を入れる時に苦労せず、効率よく作りたいなら、幅は広い方がいいです。
布の幅が狭いと、価格は手ごろですが、布面積が縦長になるため型紙が入りにくいです。
ポーチやバッグなど小物の型紙はまだしも、大人用の洋服、特に男性の洋服になれば型紙が大きくなり、なおさら入りにくいです。
それと比べて、幅が広い布は金額がお高めです。しかし、幅が広ければ布面積を広く感じやすいです。
限られた布幅の中で「あーでもない、こーでもない」と、まるで脳トレをするかのように型紙を回転させる手間がなくなるのです。
ちなみに、私は過去にも布の長さについて記事を書いています。その時には「洋服を作る時の用尺めやす」を調べたので、そちらも参考にしてみてください。
布の長さが足りないときの対処法3選!測り方などもマスターしよう♪
着物を仕立てるときの布にも規格がある
日本ならではの着物を仕立てる布は、「着尺」といいます。着尺の幅にも、このような規格幅があります。
- 小幅(並幅)…約36cm(鯨尺9寸5分)
- 中幅…約45cm(鯨尺1尺2分)
- 大幅(二幅・広幅)…約72cm(鯨尺1尺9寸)
「鯨尺」とは、鯨のヒゲをものさしの材料に使っていたことが由来となっている、長さを測る単位のひとつです。鯨尺の1尺は37.88cmですが、現在は使われていません。
洋服は袖や衿部分を切って縫い合わせるため、型紙を合わせて裁断したり、縫い合わせたり、手間がかかります。
着物を作る場合も手間はかかりますが、縦に長い布同士を横へ縫い合わせて作るため、幅も小さくなるのですね。
布の幅は最大3mくらい!ただし販売店は少ない…
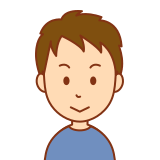
規格外かもしれないけど、ダブル幅よりももっと大きな布はないの?
180cm以上の幅が広い布なら、メーカーにもよりますが220cmや、場合によっては最大3mくらいです。
素材も、シーツ、カーテン、テーブルクロスにも使えるような、リネン、シーチング生地などがあります。
ただし、販売しているお店はネットショップや企業向けのメーカーが多く、実店舗での販売は少ないです。
なぜなら、生産や取り扱いが難しいことと、メーカーからお店まで運搬するための送料やコストが高くつくからです。
また、ネットショップで布を購入する場合はまずサンプル布を購入したいところですが、最大幅の布を特注品としているなら、場合によってはサンプル布がありません。
私が大きな布を買いに行ったときも、幅がどれもだいたい100cmでした。かわいい布を見つけても、幅が小さくて断念…を繰り返しました(笑)
このときは、「意外と幅が広い布ってないんだな。」としょんぼりしました。しかし、メーカー側のコストを考えると、納得です。
色味や質感に期待をしすぎないことと、試しに同じお店から似たような布を先に買ってみると、大きな失敗を防げそうですね。
布の幅が足りない理由は主に2つある
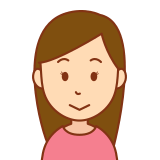
あれっ、必要な布の面積は測ってきたはずなのに、微妙に足りない…。
数cmだけ布の幅が足りない場合の主な理由は、布の耳部分を考慮していなかったことと、水通しによって縮んでしまったためです。
まず布には、生地そのものの幅をあらわす「生地幅」と、生地の「耳」と呼ばれる端の部分を除いた「有効幅」があります。
耳部分は布全体よりも色が薄かったり、ミシンで細かく穴があけられていたり、端がフリンジのようになっていたりします。そのため、縫い代には使えても、表に見える部分としては使えません。
この耳部分は両端にだいたい2cmくらいあるため、有効幅はおよそ【生地幅‐4cm】くらいです。
生地幅が120cmなら、実際に生地として使える有効幅は【120cm‐4cm=116cm】くらいですね。
しかし、すべての布メーカーが有効幅を表記しているわけではありません。
どちらの幅も表記している布はいいのですが、生地幅しか表記していない布は耳部分の長さを差し引いて選ばなければなりません。
布を選ぶときに生地幅しか見ていないと、耳部分まで布面積に含めてしまいます。そのため、耳部分を外して型紙を取ったとき微妙に足りなくなってしまうのです。
裁縫前に水通しをすると少し縮んでしまう
布が出来上がったばかりの状態(生機、きばた)は、ノリが付いたままで、パリッとしています。
いざ出来上がった後で洗濯して洋服が小さくなってしまうことを防ぐため、裁縫前には布を¥水通しします。
水通しを行うと、縦の長さだけでなく、横の生地幅も出来上がったときより最大2cmくらい縮みます。
メーカー側が出荷する前にワンウォッシュをかけて水通しすることもあれば、水通しせずに販売していることもあります。
しかし、どちらにしても生地幅は水通しをする前の状態で測っているのです。そのため、お店で実際に生地幅を測ったとき、1~2cmくらい短いこともあります。
また、メーカー側で水通しをしていない場合、購入した後、自宅で水通しをします。
すると、購入したときよりもちょっとだけ縮んでしまい、型紙を取ったときにちょっとはみ出してしまうのですね。
ちなみに私は、古い家の壁を隠すために大きなガーゼ布を買いました。インテリア用だったので水通しは必要ないかと思い、このときはそのまま使いました。
その後引越しをしたのですが、ガーゼ布をカーテンとして再利用することにしました。
1年くらい経っていたので洗濯をしたところ、ガーゼ布にシワが寄って少し短く縮んでしまいました。
あまりの短さにびっくりしましたが、カーテンとしてはちょうどいい長さになりました。自然な風合いが出て愛着がわき、今でも愛用しています♪
まとめ
- 布には、「シングル幅」「普通幅」「ダブル幅」という、3種類の規格がある
- 幅に規格を決めて生地の質をそれぞれ分けることで、お店の人も販売しやすく、買う人も選びやすくなっている
- 幅が狭い布生地は金額が安いため、購入時のコストが下がり、はぎれも少なくなり生地ロスも少なくなる
- 幅が広い布生地は、生地ロスは増えるが型紙に合わせてカットしやすく、裁縫時に効率が上がる
- 着物用の布(着尺)にも、日本独自の規格幅がある
- 布の幅は最大3m以上にも及ぶが、メーカー側のコストがかかるため、主にネットショップで販売されている
- 幅の長さは、生地の耳部分も含めた「生地幅」で表記しているところが多い
- 購入するときは、水通しして2cmくらい少し縮むことを想定して、少し長めに見積もるといい

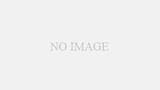
コメント