 お役立ち
お役立ち スピーチのネタを高校生向けに紹介!困ったらテーマから考えよう
高校生は勉強以外にもいろんなことに挑戦できる大切な時期です。 例えば生徒会長は朝礼や全校集会、入学式などのイベントでスピーチをする機会が多いですよね。 毎回同じようなスピーチをしていると、聞いている人たちは退屈に感じてしまい、あまり耳を傾け...
 お役立ち
お役立ち 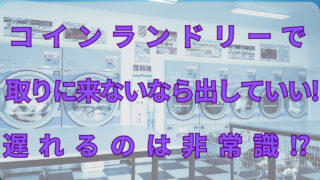 お役立ち
お役立ち  お役立ち
お役立ち 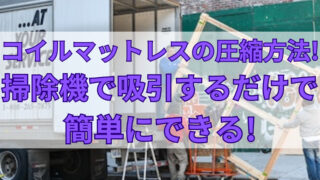 お役立ち
お役立ち